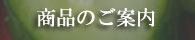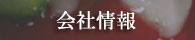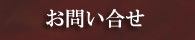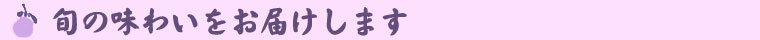
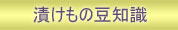
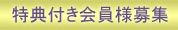
兵庫県たつの市神岡町
田中1042番地の2
tel.0791-65-0057
『漬かる』ってどういうこと?
漬けものの独特の風味が生まれるのは、野菜や漬け床が酵素の作用で分解するため。塩分によって野菜の細胞が死滅すると、細胞液が流出し、これにいろいろな種類の微生物が繁殖していきます。漬けものに欠かせない菌は乳酸菌。乳酸菌が作り出す乳酸は、漬けものの風味づけだけでなく、塩味をまろやかにする働きがあります。また適度に増えた乳酸菌は、腐敗の原因となる有害微生物の繁殖を防ぎ、漬けものの保存性を高めることにも役立っています。
漬けものに塩を使うのはなぜ?
漬けもの作りにとって、いちばんの敵はカビです。漬けものには腐敗や悪臭のもとになる腐敗菌、酪酸菌も繁殖しており、塩はこれらを死滅させ、乳酸菌などの有用微生物の繁殖をスムーズにさせる役目をしています。塩分濃度が高すぎると乳酸菌まで死滅してしまい、逆に低すぎると乳酸菌が繁殖する前に有害菌が繁殖して腐らせてしまいます。 また、野菜は塩をすると一見しおれて柔らかくなりますが、組織自体は塩によって引きしめられているため、かえって歯ざわりが良くなります。さらに、梅干やなす漬けなど、きれいに発色した色を保つのも塩の働き。塩は単に味付けだけではなく、野菜が漬かりやすくなるための脱水作用や、菌の繁殖のコントロール役など、何役もこなしているのです。
粗塩がよいといわれるのはなぜ?
昔ながらの精製法で精製された粗塩は、ミネラルを多く含み、水分も多く、粘りがあるので野菜になじみやすいというのが特徴でした。しかし、現在では精製法が変ったため、料理に利用する食塩をやや湿らせて利用するか、自然塩、天然塩と呼ばれる精製した後、改めて天然にがりを添加したものを利用します。最近ではリンゴ酸やクエン酸などを添加し、漬かりやすく工夫した漬けもの専用の塩も市販されています。 精製に精製を重ねた食卓塩は、結晶がそろっているのでさらさらしていますが、その分、野菜になじみにくく、価格も高いので漬けものには向きません。
梅にしそを入れるのはなぜ?
梅干にしそを加えると風味が増すばかりでなく、見るからにおいしそうな色の梅干になります。これは、赤じそと梅との化学反応によるもの。しその葉に含まれているシソニンと言う色素は、アルカリ性では紫に、酸を加えると赤くなるという、リトマス紙のような性質があります。梅には3.2〜3.4%のクエン酸、0.8〜1.5%のリンゴ酸が含まれているため、きれいな赤色に発色するのです。
1日1回ぬか床を混ぜなくてはいけないのはなぜ?
ぬか床をそのまま放置しておくと、酸素が無ければ繁殖できない乳酸菌が死滅し、逆に酸素を必要としない酪酸菌と言う悪臭のもとになる菌が繁殖してしまいます。ぬかを混ぜることによって、酸素がまんべんなくぬか床に行きわたり、ぬか床がリフレッシュするのです。なお、水がたまったぬか床も酸素が中まで入りにくいので、水はこまめに取り出しましょう。
みょうばんや釘がなすを色鮮やかにするのはなぜ?
なすに含まれているナスニンという色素と、アルミニウムや鉄のイオンが結びつくと色鮮やかな青紫色になる性質があります。比較的入手しやすい釘とみょうばんにはそれぞれ鉄イオンとアルミニウムイオンが含まれているので、これらを利用することが多いのです。釘は新品のものよりも、錆びているものがナスニンと反応しやすく、また、みょうばんの入れすぎは味が悪くなるので注意しましょう。