

たたら製鉄 用語集

☆ タタラ(高殿)
タタラとは野鈩(のたたら、露天精錬)の頃は精錬炉をいい、近世に、屋内精錬に
移行すると、建物をタタラ(高殿)といい、つぎに付属設備を含めたものをタタラ(
鈩)または、タタラ場と呼ぶようになった。
タタラとはタタール人(ダッタン人)の技法が中央アジアから朝鮮半島を経て日本
に伝わったものともいう。また古来日本でフイゴをタタラといっていたが、のちに製
鉄炉をさすようになったともいわれる。
☆ 天秤フイゴ
フイゴはタタラ製鉄を行う時に炉内に空気を送り火力をあげるための装置。
天秤フイゴは出雲では元禄4年(1691)、石見(島根県)では享保年間(17
00年頃)から使用したといわれる。和鋼博物館に展示のフイゴは明治24年製で、
石見の若杉タタラで使用していた一人踏みのヤグラ天秤ではある。交代ではあるが、
三昼夜の送風は過酷な労働であった。
☆ ケラ
タタラの炉(釜)底にできた鉄塊で炉をこわして引き出す。
重量は2.5〜3.5t。鋼、鉄、銑などが含まれている。
☆ 玉鋼(たまはがね)
ケラは冷却した後、細かく破砕し、玉鋼その他に分ける。玉鋼一級品は純度が極めて
高く、最上の日本刀材料で、50年経過しても美しい金属的な光を発している。玉鋼
のほかに目白、砂味(じゃみ)、ケラ銑(けらづく)があって、日本刀以外の用途に使
用した。
☆ 銑(ずく)
ケラには鋼のほかに流し銑(ずく)とかケラ銑(けらずく)とができる。流し
銑は製鉄炉(釜)の湯地口から流れ出たもの。ケラ銑はケラを破砕した時に出る銑であっ
て、いずれも鋳物の材料とか、包丁鉄の原料に使用した。炭素1.7%以下のもの。
☆ 包丁鉄(ほうちょうてつ)錬鉄(れんてつ)
銑(ずく)や歩ケラ(ぶけら)(玉鋼と銑の中間の炭素量)を大鍛冶場の火窪(ほど
)で脱炭し鍛冶して作ったもの。“割り鉄”とも“延べ鉄”ともいい、低炭素の錬鉄
で、刀工はこれを刀の心鉄にするが、一般的には日用刃物・釘その他の柔らかい鉄材
料に使用した。
|
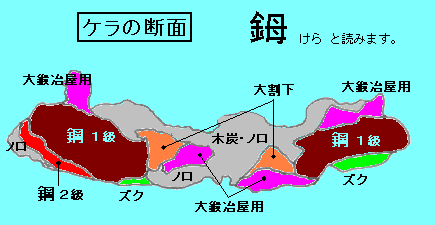

|

|
| 戻る | 進む |