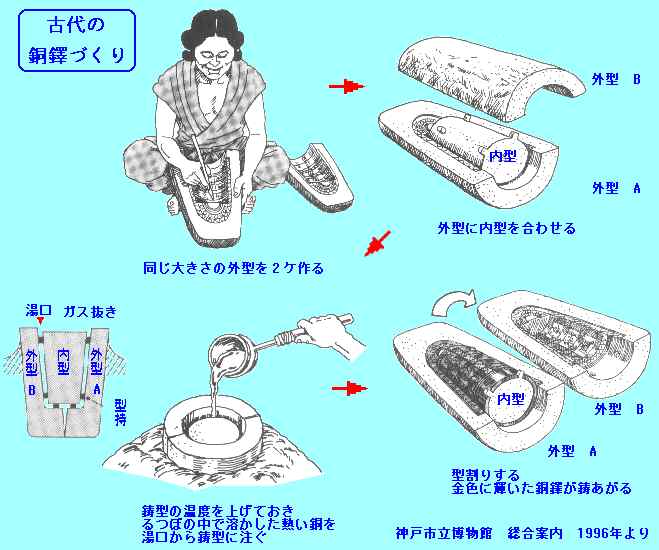銅鐸づくり (10月号)
弥生時代の銅鐸や武器形祭器は、銅とスズの合金(青銅)を溶かして鋳型に流し込んで作る
鋳物です。武器形祭器は同じ形に彫りくぼめた2個の鋳型を合わせて、そのなかに青銅を流し
込む方法で鋳造されたものが多く、銅鐸のように中空の製品は2個の外型のあいだに内型(なかご)
を入れ、そのすき間に青銅を流し込む方法で製作されている。古い段階の銅鐸の鋳型は石製で、
弥生時代中期中ごろ以降は砂型に変化すると推定されています。
銅鐸の鋳型は、大和、河内、摂津、山城など、後に畿内と呼ばれる地域で多く発見されているほか、
播磨、越前、肥前、筑前のどから発見されており、武器形祭器の鋳型は北九州におおく、機内でも
数例知られている。
青銅器に使われた、銅やスズがどこで産出したものかわかっていません。銅が文書に現れるのは
以下です。
「人皇43代元明天皇の元年(708年)、武蔵の国より銅が献上される。これによって年号を和銅と
改め、(中略)しかし、42代文武天皇の2年(698年)に因幡周防の国より銅の鉱(あらがね)を
献上するとあるので、和銅がまったく最初とはいえない」
(袖鑑萬物蔵・初編・20頁)
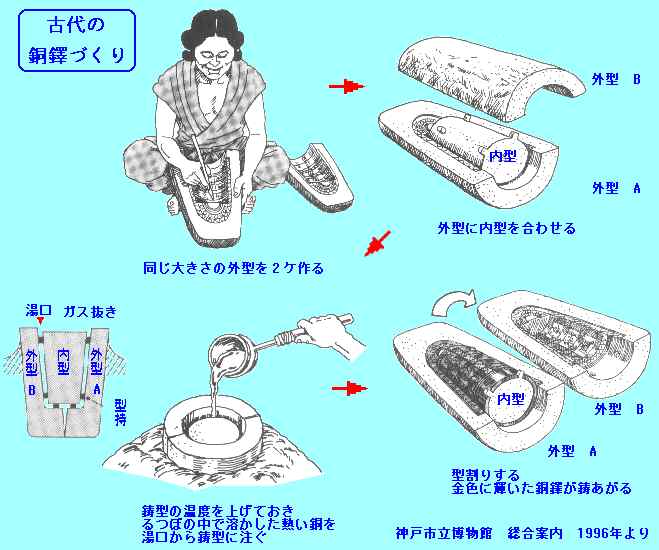
参考図書
神戸市立博物館 総合案内 1996年
古文書から学ぶ 江戸の知恵・江戸の技 北田正弘 日刊工業新聞 1998年
感想やご意見をお送りください。投稿も大歓迎お待ちしています。

|

|
|
戻る
|
進む
|