代わりばんこ
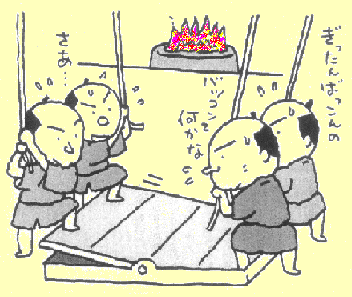 代わりばんこってなに? 秋田県 沢口喜代子さん
代わりばんこってなに? 秋田県 沢口喜代子さん
昔、製鉄にはふいごと呼ばれる空気を送る大型の装置が必要でした。そのふいごを
踏む人を「番子」(ばんこ)といい、力仕事のため交代で作業をしていたところから、
「代わりばんこ」という言葉が生まれました。
代わりばんこという言葉は、普通「交代に」とか「順番に」の意味で使われます。
音の感じがユニークで何かの略語?という雰囲気もしますが、調べてみたらこんな
由来がありました。
昔、鉄を作る際には、炉に空気を送りつづけるため、ふいごと呼ばれる装置を使って
いました。ふいごにはいろいろな形や大きさがありますが、江戸時代に鉄を作る場合に
使われていたのは、人が足で枚を踏む形式のもの。この板は畳2畳分ほどもあり、
とても力のいる大変な仕事でした。
そのため、作業に当たる人は、何人かが組みになり、交代しながらふいごを踏み
つづけたのだそう。この人たちを「番子」と呼んでいたことから、代わりばんこという
言葉が生まれたのです。
ちなみに、土俵上で力士が、勢いあまって踏みとどまろうとしっつも「おっとっと」
と数歩あゆんでしまうことを「たたらを踏む」と表現します。この「たたら」は、
サンスクリット語で「ふいごの踏み板」という意味です。
大ヒット映画「もののけ姫」にも、女性たちが力を合わせて巨大なたたら(ふいご)
を踏むシーンが登場します。と聞くと、その大がかりな仕組みや作業の大変さにピンと
くる人も多いと思います。
子どものころから「代わりばんこにみんなで仲よくね」などと使ってきた言葉ですが、
その語源は、まさに「代わりばんこ」でなければ勤まらない、とても大変な仕事だったんですね。
取材・文/笹原知子
取材協力/衣川製鎖工業㈱
参考文献/「語源面白すぎる雑学知識』(青春ベスト社)
『採鉱と冶金』日本評論社)
『江戸語辞典』(東京堂出版)
生活便利マガジン『オレンジページ』 2,000年3月17日発行
あなたに代わって見聞帖 より転載

|

|
|
戻る
|
進む
|


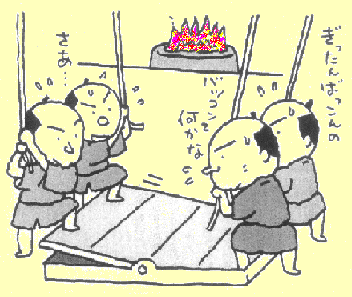 代わりばんこってなに? 秋田県 沢口喜代子さん
代わりばんこってなに? 秋田県 沢口喜代子さん
